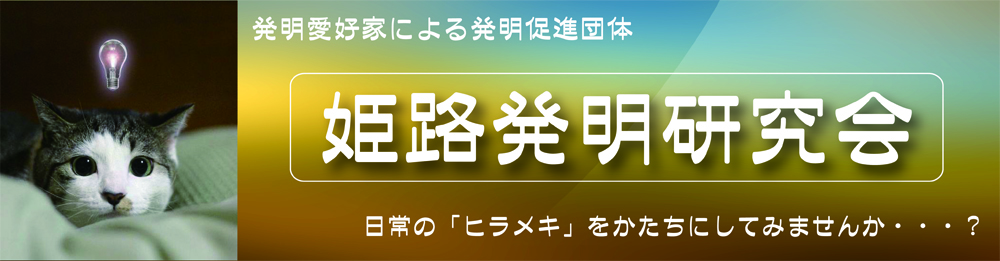会長挨拶
令和7年度挨拶
「 傘寿を越えて思う 」
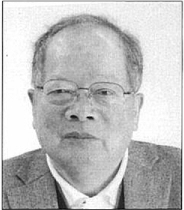
姫路発明研究会
会長 中村 隆弘
今年の正月で傘寿となりました、区切りの良い年令になれば孔子の言葉を思い出しているのです。
吾十有五而志于学 我十五にして学に志す
三十而立 三十にして立つ
四十而不惑 四十にして惑わず
五十而知天命 五十にして天命を知る
六十而耳順 六十にして耳したごう
七十而従心所欲、不踰矩 七十にして心の欲する所に従えども、のりをこえず
昔は80歳まで生きる人がいないのか80歳が無いのです。今は人生100年時代とか言われていますが私は今年正月から親しい身近の人が3人亡くなりました。兄のようにしていた従兄(88歳目前)、義姉(85)、竹内県会議員(50)です。竹内先生は市議に当選された時からのお付き合いで平成22年から当会の名誉会員になっていただき、事あるごとに色々と相談やお言葉をいただいてきました。突然、理不尽な事で亡くなられ義憤を感じています。自分の当選を目指さず他人を応援する為の立候補、法律で決まっていないとして立候補を受け付けた選挙管理委員会、なぜ選挙管理委員会自体で受付拒否しないのかわかりません。後日、総務省に決めてほしいと申し入れたとのことですが自分達の責任で決めることが出来無いのでしょうか、おかしな事です。昔から不文律というものがあったはずです、法を守らなくても自分の理屈で良いのだと言って実行する、党を除名されれば辞任するという誓約書まで書いたものを反故にできる、その心が理解できません。同様に、指示され金銭を得る為には手段を選らばない闇バイトなど絶対に許せなかったことです。
また、他県の知事選に立候補して兵庫県で選挙演説をしているなど意味が分かりません。人の心が判らず指摘されたことも、そんな考えもあるのでしょうと知らず存ぜず県政を前に進めたいと言って通用するのでしょうか、パワハラと思ったら"それはパワハラですよ"と上司でも言おうではありませんか。
そのためには自分に自信を持つ必要があり、自分を磨く姿勢を持ち続けることが必要と思います。私達日本人は自信をもって何事にも当たろうと言いたいのです。賃金が安いから、しんどいからなど、技術者が激減しています。政治家に技術者がいないのが原因か、また海外でものづくりをやれば安くできると言って海外展開しその結果、技術が海外に流出し国内に技術が残らず、技術で中国に負け、国際社会から置いて行かれそうになっている現状を少しでも良い方向に向けたいと思っています。
令和6年度は北川巧さん、小寺啓三さんの発明が特許になり、高野博文さんの発明が商品化できそうです。また少年少女発明クラブもチャレンジコンテストで全国大会に2チームが出場できました。
今年度もよろしくお願いいたします。
私の現役時代によく言ってたことは下記でした。意味を考えてください。
20代は 体で仕事を
30代は 頭で仕事を
40代は 顔で仕事を
50代は 腹で仕事を
60代は 心で仕事を
参考になればですが、今では仕事を社会貢献に修正したいと思っています。
中村 隆弘
姫路少年少女発明クラブ/会長
光テクノ株式会社/代表取締役
http://www1.winknet.ne.jp/^hikaritech/
■事務所:670-0976姫路市中地17-1
TEL:090-1130-1768
E-mail:
ctnaka@mineo.jp